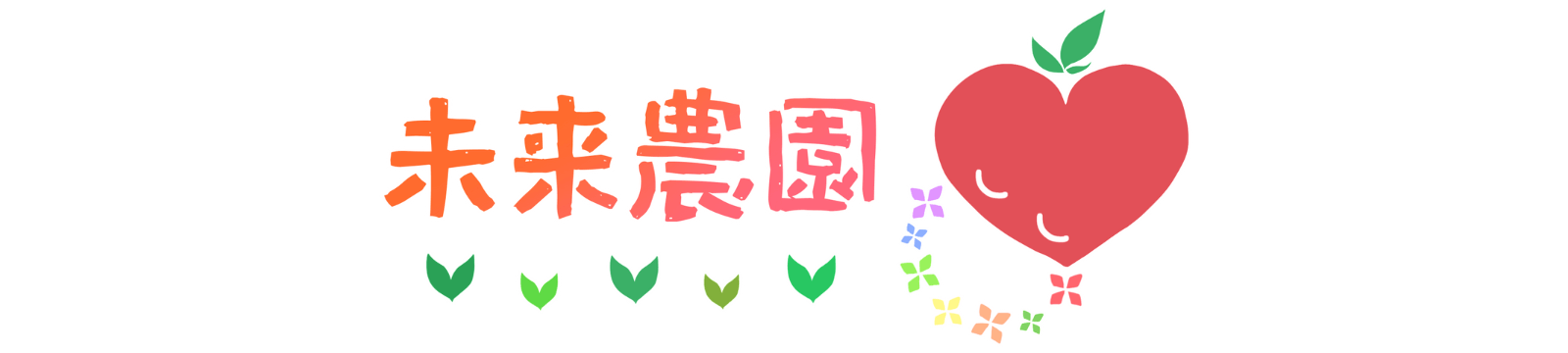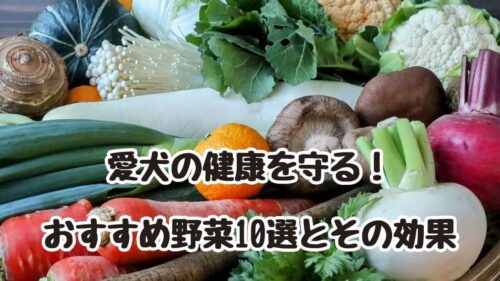夏野菜の定番、なすび。愛犬にも食べさせてあげたいですよね。
結論から先に言うと、犬にナスを与えても大丈夫です!
なんですが、ちょっと気になるウワサ話もあるので、そのあたりも含め、今回はナスを与えることのメリットや与える際の注意点などを詳しく解説していきます。
ナスにしかない栄養素「ナスニン」が持つすごい作用は犬にもメリット

ナスがなぜ濃い紫色をしているのかというと、これはアントシアニンという成分が含まれているためです。
このアントシアニンの中には『ナスニン』と呼ばれるナス特有の栄養素があり、ブロッコリーやホウレン草より強い抗酸化作用があることで知られています。
また、夏野菜のなかでも特に体を冷やす効果が強いため、夏バテ予防のために食べさせたい食材のひとつです。
ナスは94%が水分でできているため、他の野菜に比べると栄養価はそれほど高くないのですが、ナスからしか摂れない栄養素もあるため食べる価値は十分にあると言えます。
栄養面で言うと他にもこんな効果が期待できます。
- 血栓ができるのを防ぐ
- 老化予防
- 利尿作用
- 便秘解消
- 目の疲労を改善
- 血圧を正常に保つ
- コレステロールの吸収を抑える
関節炎に悪いという話は本当か?ナスを犬に与える際の注意点

実はナスには天然の毒「アルカロイド」がごく微量含まれています。
これはナス科に属するほとんどの野菜(ピーマン、じゃがいも、トマト等)に共通して含まれる成分です。
それに関連して、『関節炎の子がアルカロイドを摂取すると関節の修復ができなくなる』という説があるのですが、単なる一説であっていまだに関連性は証明されていません。
もし「愛犬が関節炎を患っている」という場合は念のためやめておくというのも手だと思います。
いまは品種改良が進んで可食部にはアルカロイドが含まれないようになっているそうなので、健康な子に食べさせる分にはまったく問題ないと考えています。
与えてはいけないのは葉や茎で、多めのアルカロイドが含まれており、下痢や嘔吐を引き起こす可能性があります 。
ナスが犬の体に与える影響
犬にナスを与えることは基本的に安全とされています。
ただし、適量を守って与える必要があります。ナスには93%が水分で構成されており、少量であれば水分補給の役割を果たします。
しかし、過剰に摂取すると消化不良や下痢の原因になることがあります。
また、「犬にナスを食べさせてもいいの?」という問いには、調理法や量を工夫すれば大丈夫というのが答えになります。
ただし、ナス科の野菜特有の成分であるアルカロイドには注意が必要です。
ナスに含まれる栄養素とその効果
ナスは栄養価が高く、犬にとってもメリットがあります。
特に皮に含まれる「ナスニン」というポリフェノール成分は抗酸化作用があり、老化防止への効果が期待されています。
また、カリウムは利尿作用があり体内の余分な塩分を排出する働きがありますが、高齢犬や腎臓疾患がある場合には注意が必要です。
同様に、豊富な食物繊維は腸内環境を整える効果がありますが、摂取量が多すぎると逆に消化を妨げる可能性があるため適量を心がけましょう。
アルカロイド成分についての注意
ナスを含むナス科の植物には、微量ながらアルカロイドという成分が含まれており、摂取量によっては体に影響を与えることがあります。
特にソラニンと言われる成分は、過剰摂取すると消化器の不調や神経系の問題を引き起こす可能性があります。
犬に与える場合は、皮や種部分を取り除き、消化しやすい形で与えることが重要です。
アルカロイドの影響を最小限に抑えるためにも、必ず加熱してから与えるようにしましょう。
子犬や老犬(シニア犬)に与える際の注意点
子犬や老犬にナスを与える際は、特に注意が必要です。
子犬の場合、消化酵素が未発達なため、ナスのような消化に時間がかかる野菜は適応しづらいことがあります。
老犬に関しては、腎臓や肝臓の機能が低下している可能性があるため、カリウムやナスに含まれる特定成分が負担となる場合があります。
どちらの場合も、無理にナスを与える必要はなく、与えるとしてもほんの少量から様子を見ながら始めることをおすすめします。
犬にナスを与える方法:安全に与えるためのステップ
適量とはどれくらい?適切な分量の目安
ナスは犬が食べても大丈夫ですが、量には気を付ける必要があります。
ナスは93%が水分でできておりカロリーは低いものの、過剰な摂取は消化不良や下痢を引き起こす可能性があります。
適量の目安として、小型犬なら一口サイズを1~2個分程度、中型犬ならその倍程度を与えるのが理想です。
なお、ナスを主食として与えるのではなく、あくまで健康的な補助食品として少量ずつ与えるようにしましょう。
調理方法のポイント:生、茹でる、焼く
ナスは生でも加熱しても犬に与えることができますが、それぞれに注意が必要です。
生で与える場合、皮が硬く消化に時間がかかるため、細かく刻むかすり潰して与えることをおすすめします。
一方、茹でたり焼いたりすることで、柔らかくして犬にとってより消化しやすい状態にすることができます。
ただし、調理時に味付けをすることや揚げ物にすることは避けてください。
また、ナス特有の栄養素「ナスニン」を摂るためには皮ごと食べる必要があるため、食べさせるときは皮と中身を一緒に焼いて与えてください。(煮るのは✖。栄養分が水に溶けだしてしまいます)
特に、犬に与えるナスは塩や油分をまったく含まないことを徹底しましょう。
皮を与えるべきか?取り除くべきか?
ナスの皮にはポリフェノールの一種であるナスニンが含まれ、抗酸化作用が期待されています。
しかし、皮は消化に時間がかかるため、小型犬や消化能力が弱い犬には取り除いてから与えるのが安心です。
中型犬や大型犬で健康状態が良好な場合は、皮を取り除かなくても構いません。
ただし、どの場合でも細かくカットしてから与えることが大切です。
また、ナスの茎や葉の部分はアルカロイドを多く含み、犬にとって有害となるため絶対に与えないようにしましょう。
与える頻度:毎日は避けた方がいい理由
ナス自体は犬にとって安全な野菜ですが、栄養バランスの観点から毎日与えることはおすすめできません。
ナスには利尿作用があるカリウムが含まれており、摂りすぎることで犬の腎臓に負担をかける可能性があります。
また、ナスは体を冷やす性質があるため、特に冷えが原因で不調を起こしやすい犬には頻繁に与えるのを避けましょう。
週に1~2回、適量を守って与えるのが理想的です。
犬にナスをあげてはいけないケース
健康状態によるリスク(甲状腺や結石など)
犬にナスを与える際には、健康状態によるリスクを十分に考慮する必要があります。
特に甲状腺に問題がある犬や、結石を患っている犬には注意が必要です。
ナスに含まれるカリウムは利尿作用があり、一部の犬には健康的に思える効果が期待できる一方で、結石のある犬の場合には症状を悪化させる可能性も指摘されています。
また、甲状腺の疾患を抱える犬は、ナス科の野菜に含まれる特定の成分が体調に影響を与える可能性があるため、獣医に相談した上で与えるかどうかを判断した方が良いでしょう。
アレルギー症状とその見分け方
犬がナスを食べることでアレルギー反応が出る場合もあります。
一般的な症状としては、皮膚のかゆみ、発疹、涙目、嘔吐、下痢などが挙げられます。
初めてナスを与える際は、少量から試してみて、犬の体調に変化がないかよく観察することが重要です。
また、ナスに含まれる特定の成分がアレルギーの原因となる可能性もあり、症状が出た場合はすぐに与えるのをやめて獣医に相談してください。
注意深く与えることで、アレルギーのリスクを最小限に抑えることができます。
体を冷やしやすい犬がナスを摂取するリスク
ナスは体を冷やす性質を持つ食材であるため、体質的に寒がりな犬や冷えに弱い犬には向いていない可能性があります。
冷えが進むと、消化能力の低下や体力の減退を引き起こす恐れがあります。
特に体温管理が難しい子犬や老犬(シニア犬)に与える場合は、量を控えめにし、加熱調理した上で体に負担がかからないように工夫することが大切です。
また、季節的にも寒い時期にはナスを避け、別の野菜に切り替えるのも一つの選択肢です。
過剰摂取による下痢や吐き気のリスク
ナスは少量であれば犬が食べても大丈夫な野菜ですが、過剰に与えると下痢や吐き気を引き起こす可能性があります。
ナスの93%は水分でできているため、水分過剰摂取による影響も考慮する必要があります。
また、ナスニンなどの成分が犬の胃腸に刺激を与えすぎる場合もあるため、適量を守ることが不可欠です。
ナスをあくまで補助食品として少量ずつ与えることを基本とし、過剰摂取を避けることで健康被害を防ぐことができます。
ナス以外にも注意が必要な食品とその代替案
ナスに似た食材で注意が必要なもの(例:ブロッコリー、トマト)
ナスに似た食材として、ブロッコリーやトマトも犬に与えられる食品として知られていますが、注意が必要です。
ブロッコリーは栄養価が高く、ビタミンCや食物繊維が豊富ですが、甲状腺の疾患を持つ犬や結石のリスクがある犬には控えることをおすすめします。
一方、トマトの場合、熟した部分は少量であれば大丈夫ですが、未熟なトマトや葉、茎に含まれるソラニンという成分は犬に対して毒性があるため注意が必要です。
これらの食材を与える際には、適切な量と調理法に気を配りましょう。
代替としておすすめの野菜や果物
ナスの代替としておすすめの野菜には、サツマイモやカボチャがあります。
これらは犬に必要なエネルギーや栄養を補うのに適しており、特に茹でたり蒸したりすると消化が良くなります。
また、果物ではリンゴやブルーベリー、バナナなどが挙げられます。
リンゴは食物繊維が豊富で腸内環境を整える効果がありますが、種や芯は取り除く必要があります。
バナナはエネルギー源として優れていますが、糖分が多いため少量にしましょう。
犬の健康状態や好みに合わせてこれらの代替食品を取り入れてみてください。
季節に応じた食材選びのポイント
季節に応じた食材を選ぶことは、犬の体調管理にも役立ちます。
夏には水分が多く、熱中症を予防できるような食材、例えばキュウリやスイカがおすすめです。
一方、冬は体を温める効果のあるカボチャやサツマイモが適しています。
旬の食材は栄養価が高いうえ、手頃な価格で手に入ることも利点です。
ただし、どの季節でも過剰摂取は禁物で、適量を心がけて与えるようにしましょう。
季節ごとの食材選びを意識することで、愛犬の健康をより効果的にサポートすることができます。
農家が教えるおいしいナスの選び方
みずみずしく新鮮なナスの選び方は主に以下の4つです。
- ヘタの切り口が新しく、枯れている部分がない
- ヘタがとげとげしく固い
- 皮に傷やシワがない
- 濃い紫色でハリ・ツヤがある
以上がおいしいナスを選ぶコツです。
ぜひあなたの愛犬に良いナスを選んであげてくださいね!
家庭菜園で無農薬のナスを作るのも良いのではないでしょうか?